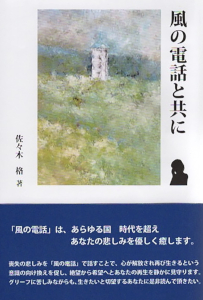仏教に「因果の道理」という考え方がある。運命を行い(原因)の結果だとする考え方だが、私たちは希望をもって未来を見る時、その人生に対して肯定的であればある程「未来は決まっていない、運命など存在しない、自分の力で未来を切り開く」という想いを抱く。良い結果が出た時には、けっして運命だとは言わない。自分が頑張ったからだと言うだろう。
一方、「私たちは既に起こってしまった過去の出来事を悔いを持って見つめる時、あれは自分の人生に与えられた運命であった」という想いを抱く。ということは、運命というのは結果に対してだけ現れ、それも自分の意志と相容れない結果に対してのみそのように感じるのかも知れない。そして、それを運命であると受け入れるようになる。
自分の運命(結果)を良いものにするためには。原因にあたる行動が重要になる。アメリカの心理学者で哲学者のウィリアム・ジェームスは心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わると語っている。仏教でも、心がけを変えると運命が変わると説き、洋の東西を問わず運命はあることを前提にし、自分の行動次第であるとしている。
だから、自分が考え行動した通りの人になると言える。大根の種をまけば大根がなり、人参にはならない。ヒマワリの種をまいてチューリップが咲くことはない。自分の「心がけ」ひとつ、なれないまでも近づくことは出来ると思っている。