3年ほど前より「風の電話」を訪れる外国人が増えてきました。昨年からはその傾向が更に強くなっています。ブログを見ても、閲覧しているのは国内だけでなく、半分は外国からでアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、シンガポール、香港、オーストラリア、台湾、中国,ニュージランド、等々の国々の方である。論理・合理的と見られている多くの外国人がなぜなのでしょうか?
愛する人を失った時、その悲しみは何処の国でも、何時の時代でも変わらない普遍的なものです。そして、グリーフを抱え会えなくなった人にもう一度心を通わせたい、想いを伝えたい、再び繋がりたい、再開したいと望む気持ちも同じです。亡くなったのでもう繋がることは出来ないとそこで断ち切られてしまったなら、後に残るのは悲しみと絶望感だけです。亡くなっても繋がることが出来るという想いが、残された方に生きる夢や希望を与えてくれます。亡き人と想いを繋ぐという事はそれほど大切なことであり命の重さ、命の尊さに気づかされます。
人はグリーフを抱え生命力が低下した時、理詰めの論理より情緒で考え、感情で行動する傾向にあります。なぜなら、隙の無い論理で構築されるところに人の情が求める「救い」の要素は余りないと考えます。
「風の電話」は見えないものを観るとか、聞こえないものを聴く、とか、電話線が繋がっていないので何処でも繋がれる等々、あり得ないことであっても「何かこうあって欲しい」とか「実際には無理だと思うけれどなんとかならないだろうか」と言うように論理的ではなく、漠然としている反面見果てぬ夢とか希望が持てると感じられることが大切だと考えています。
現実の世界を生きることを考えた場合、「曖昧」な漠然としている方がむしろ合理的な判断や対応をすることが出来ると考えられます。そもそもこの世界が白や黒、右や左で割り切れるのであれば私たちは苦悩したり、悲しみに絶望するなどあり得ないことだろうと思います。
論理・合理的な外国人でも愛する人を失なった時、何かに「救い」を求める心情には変わりはなく、日本人の持つ「曖昧な合理性」に「救い」を見出すのではないでしょうか。
今年3月時点で、世界中に300箇所を超える「風の電話」が設置されています。そのことが「風の電話」の持つ「曖昧な合理性」の力を物語っていると考えます。
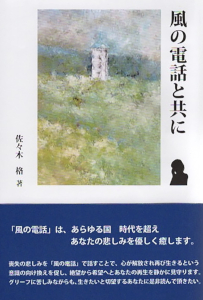 。
。

