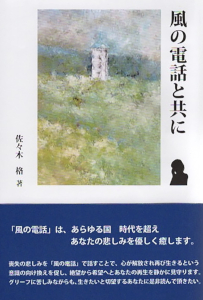人には他人から良く思われたいというエゴがあります。人から何か批判されると、それを受け止められずに、傷ついたり、落ち込んだりします。
それらはすべて、自分の心が苦しみを生み出していると言えます。あなたの心が苦しみを拾っているのです。批判を否定的にとらえ、苦しいものとして受け取っているのは、それらに価値を与えているあなたの心なのです。
ある人から意地悪されたから苦しいのではなく、あなたがその時、そこにこだわり「ああ困った」とか「ああ嫌だ」と否定的に捉えてしまうところに苦しみを抱える原因があると考えてください。
ストレスもそうです。原因はいろいろですが、実は自分の勝手な思い込みが原因となっていることがほどんとなのです。何かを期待して思い通りにならないことからくるイライラや、自分がこれだけやっているのにという被害者意識などがそうです。
世の中は、自分一人で生きているのではなく人と人、人と自然など様々なものが皆関連しあって生きていますから、自分の思う通りに行かないことが当たり前と考え、心をリラックスさせましょう。