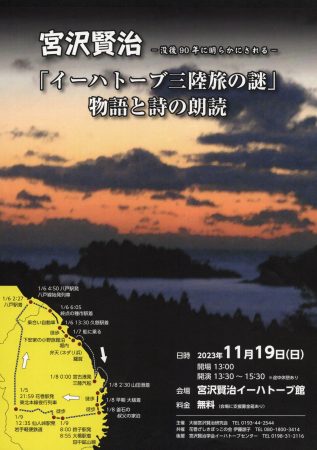皆さん、新年あけましておめでとうございます。今年も、どうぞ宜しくお願いいたします。
宮沢賢治は、100年前のちょうど今日(1925年1月5日)彼の人生の大転換を決意したと考えています。 それまでの彼は、法華経の「利他精神」を文学による布教を目指したフィクションの創作者でした。いわば、虚構、作り話、物語の作り手だったわけです。しかし、前年1924年に初めて自主出版した「春と修羅」「注文の多い料理店」が不評だったことから、賢治は「農民の幸せ」を願いながらも本当に百姓の気持ちを理解していないのではないかと自省します。又、農学校で生徒たちに学校で学んだ知識や技術を実際に生かすため、卒業したら百姓になることを勧めたが、現実には思う通りにはいかなかった。更に、生徒に「百姓をやれ」と進めながら、自分は教師という職業について安閑としていることに自己矛盾を感じるようにもなっていた。この様な様々な思いが交錯した結果として、賢治は教師を辞めて自ら一人の百姓になるという行動に踏み出すことになったのです。それが100年前の今日なのです。
人も、社会も、何時でも変わることが出来ます、変わらなければ停滞が起きます。停滞は、水の流れが示すようにいづれ腐ってしまいます。そうさせないためにも変わることが必要なのです。それも善く変わることです。悪く変わつては元も子もありません。そのためには、私たちが良く考えて行動することです。新年を迎えて改めて考えました。

 元々、日本人の神々は自然界の物や現象にあって、人々の日々の営みを助け或は、祟って病気や死を招くと信じられていました。人々は神の存在を実感し、お願いし、鎮魂の祭り等を行ってきました。しかし、これ等の神々は次第に歴史上の偉大な人物の霊と共に、神道の神々と変わってきました。この傾向は近代、現代になり先祖との関係に変化してきました。自分の親や先祖は死んで離れてしまうのではなく、死後も自分たちのことを見守ってくれる存在。いわゆる、仏と神の一体化の傾向が感じられます。
元々、日本人の神々は自然界の物や現象にあって、人々の日々の営みを助け或は、祟って病気や死を招くと信じられていました。人々は神の存在を実感し、お願いし、鎮魂の祭り等を行ってきました。しかし、これ等の神々は次第に歴史上の偉大な人物の霊と共に、神道の神々と変わってきました。この傾向は近代、現代になり先祖との関係に変化してきました。自分の親や先祖は死んで離れてしまうのではなく、死後も自分たちのことを見守ってくれる存在。いわゆる、仏と神の一体化の傾向が感じられます。